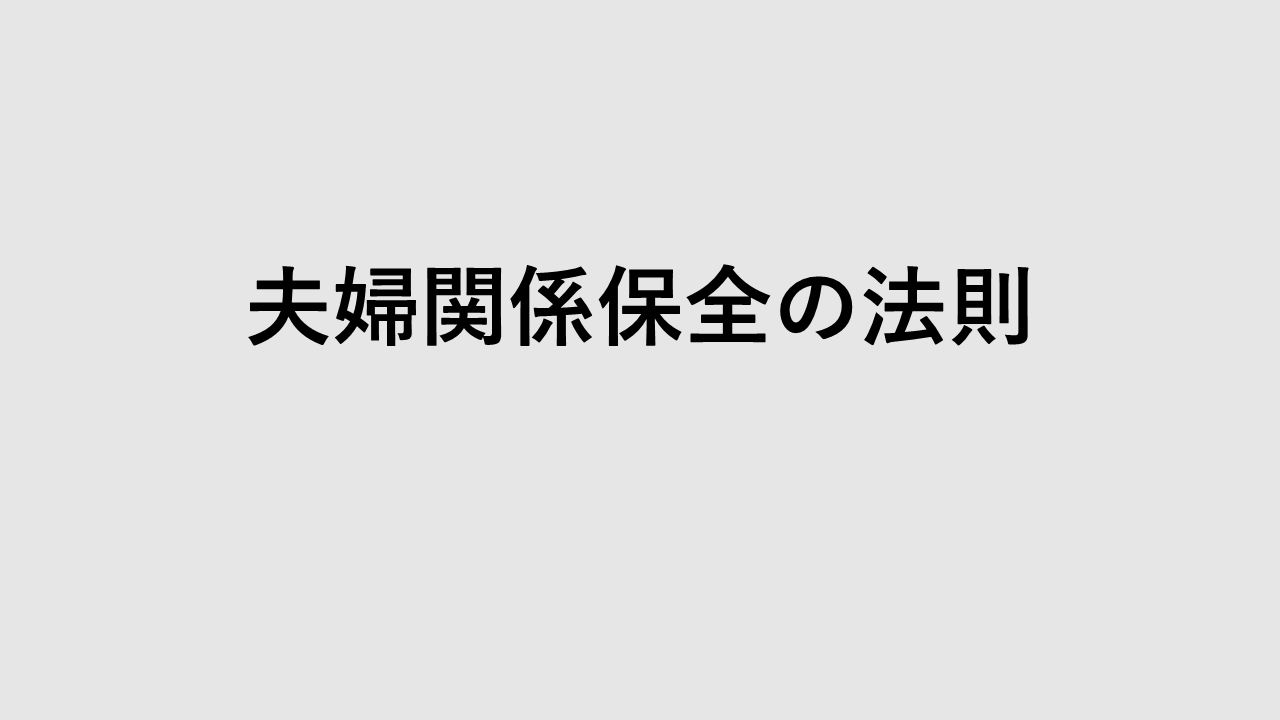昭和のころ、私は法律を学ぶ中で「夫婦関係保全の法則」という言葉に出会った。
それは、夫婦というものは社会の基盤であり、法はそれを守るべきだと説く学説だった。
私はその一言に支えられ、迷いや葛藤のなかでも「夫婦は守るべきものだ」と信じて生きてきた。
しかし、時代は変わり、判例は「破綻主義」へと傾き、学者はその流れに従ってしまった。
かつて確かに存在した「夫婦関係保全」という学説は、法学界から跡形もなく消された。
まるで、初めからなかったかのように。
その結果、離婚は「個人の自由」として容易に肯定されるようになったが、犠牲になったのは子どもたちだ。
親の都合で居場所を失い、不登校や貧困、孤立へと追いやられる。
社会はその代償を抱え込みながら、誰も責任を取らない。
本質は、法律家が「夫婦を守る」ことよりも「事件を処理し、件数を増やすこと」に傾いたところにある。
そこに、いまの社会悪の根があると私は思う。
私は学者ではないが、かつて「夫婦関係は保全すべき」と堂々と語られた時代があったことを記憶している。
その思想は消されたが、私にとっては確かな道しるべだった。
そして今もなお、子どもを犠牲にしない社会を願う者として、この証言を残しておきたい。
夫婦関係保全の法則とはなんでしょう。
昔の家族法では、夫婦は社会の基盤だから、よほどの事情がない限り離婚は認められないという考え方が強くありました。
この考え方を「夫婦関係保全の法則」と呼びます。
• 夫が浮気をしたとしても、
• 夫婦の仲が悪くなったとしても、
- *「それだけでは離婚できない」**というのが当時の立場でした。
法律は「夫婦は簡単に別れてはいけない」「家庭を守ることが優先」と考えていたのです。
⚖️ 法的な背景
• 戦後の民法(第770条)でも、離婚原因は限定的でした。
例:不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、強度の精神病など。
• しかも、「夫婦関係を回復する余地がある」と判断されれば、離婚請求は棄却されました。
• 裁判所も「夫婦はできるだけ関係を続けるべき」という姿勢で判断していたのです。
💡 現在との違い
• 今は「婚姻が完全に破綻しているかどうか」を重視する 破綻主義 が定着。
• 夫婦仲が修復不能なら、離婚は認められる傾向にあります。
• その結果、昔のような「夫婦関係保全の法則」は、学説から姿を消しました。
「夫婦関係保全の法則」とは、家庭を守ることを最優先にし、多少の不仲や不貞があっても、簡単には離婚を認めなかった昔の法の考え方です。
昔の考えですが、いまは破綻主義なので、夫も妻も、家庭が壊れれば離婚できます。
それは自由である反面、子どもや家族の安心をどこまで守れるのかという課題を残しています。
🌟 この本文を基に、子供向けの寸劇台本を作成してみました。
📄 [こどもの思い劇台本を作成しました。]