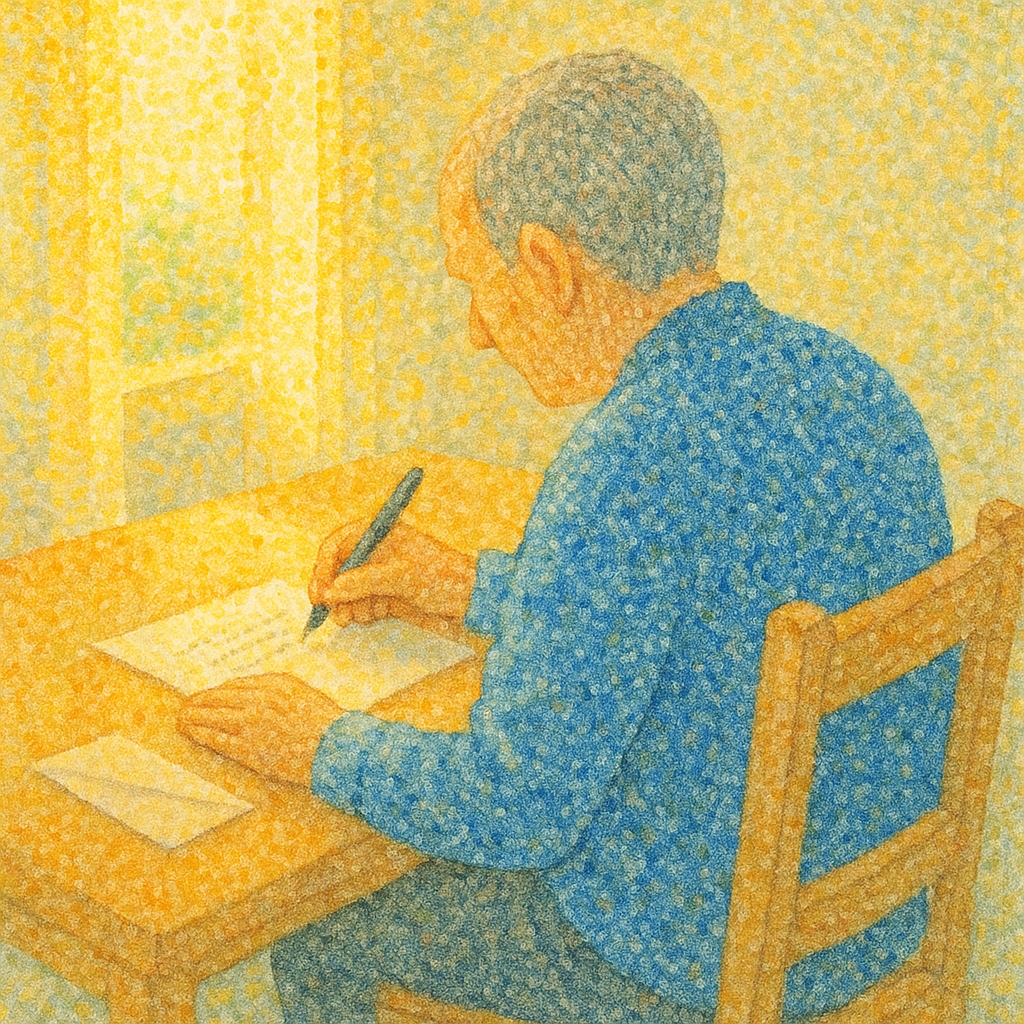昔の人たちは、いわば「収入そっちのけ」で結婚していました。
それは今とは違って、「結婚ありき」の人生設計が当たり前だったからです。
現代の流れを見てみると——
1. 結婚しました。
2. 子どもができました。
3. 離婚したいです。
4. おじいちゃん・おばあちゃん:「ちょっと待ってよ…」
こんな展開も珍しくありません。なぜこんなにも変わってしまったのでしょうか?
昔の人が「お金がなくても結婚できた」4つの理由
① 家を継ぐ・家庭を持つことが“前提”だった
昔の結婚は、恋愛よりも「社会的な義務」や「役割」の色が濃いものでした。
「男は所帯を持って一人前」「女は嫁に行って一人前」――そんな価値観が根強く、
結婚しないという選択肢自体がなかったのです。
② 家族全体で生活を支え合っていた
三世代同居が一般的で、若夫婦の生活は親や兄弟によって支えられていました。
農地や家業の引継ぎも含めて、「家族という単位」で生きていたのです。
③ 生活水準が低く、“ないのが当たり前”だった
冷蔵庫も洗濯機もない生活。オムツは布、離乳食は手作り。
質素が当たり前だった時代、「贅沢」の基準自体が今とは全く違っていました。
④ 「どうやってやりくりするか」が基本だった
足りないのが当たり前。
服はお下がり、家は借家、食料は畑から。
親戚や近所が自然に助け合う中で、無理なく暮らしていたのです。
「昔」と「今」の結婚、こんなに前提が違う
昔の結婚は、「社会的な義務」から始まっていました。
「男は所帯を持って一人前」「女は嫁に行って一人前」――という価値観のもとで、結婚するのが当然とされていたのです。
一方、現代では、結婚はあくまで個人の選択。結婚しない自由も当たり前に尊重される時代です。
経済面でも、昔は「最低限あればなんとかなる」とされていました。
貧しくても工夫して暮らし、周囲と助け合って生きるのが普通だったのです。
今では、結婚前から安定した収入や十分な貯蓄が求められ、準備不足での結婚は敬遠されがちです。
住まいについても、昔は親元や借家暮らしが普通で、「家がないから結婚できない」という発想はあまりありませんでした。
しかし現代では、持ち家や住宅ローンが“結婚後の当たり前”とされる傾向があります。
子育ても変わりました。
かつては、祖父母や親戚、近所の人など、“みんなで育てる”のが当たり前でしたが、今は核家族が中心。
夫婦だけで育てることが前提となり、精神的・物理的な負担が重くのしかかります。
そして何より、昔は「なんとかなるさ」の精神で人生を進める人が多かったのに対し、
今は「ちゃんと準備しなきゃ」という慎重な姿勢が主流です。
今だからこそ、冷静に「原因」を分析しよう
お互い収入があれば、家庭内の問題も、ある程度は“お金”で解決できます。
例えば、役割分担のバランスが崩れていたら、臨時で家事代行やヘルパーさんを頼むという手段もあります。
その費用をどう負担するかは、話し合いで決めることができるのです。
また、モヤモヤを放置せずに、お互いの思いを明文化して確認し合うこともおすすめです。
提案:はじまりノートとフューチャーノートをつくりませんか?
「エンディングノート」は人生の締めくくりのためのノートですが、
その前段階として——
– はじまりグノート(始まりの確認書)
– フューチャーノート(未来の共有ノート)
をつくってみませんか?
これらは、お互いの考えや希望を共有するための“書面のキャッチボール”です。
たとえば、内容証明でお互いにやりとりすれば、「夫婦間の証明書」として、かたちに残すこともできます。
最後に:TGSは、いつでもご相談に応じます
失ってしまった家庭のシステム(決めごと)をもう一度ご一緒に構築しましょう。
家庭の悩みも、暮らしの中の不安も、
ひとりで抱え込まず、行政書士という“第三者の知恵”を活用してください。
TGS行政書士事務所では、夫婦間の合意書作成、生活設計の相談、
そして未来に向けた「ノート」の書き方までお手伝いします。
どうぞ、気軽にご相談ください。